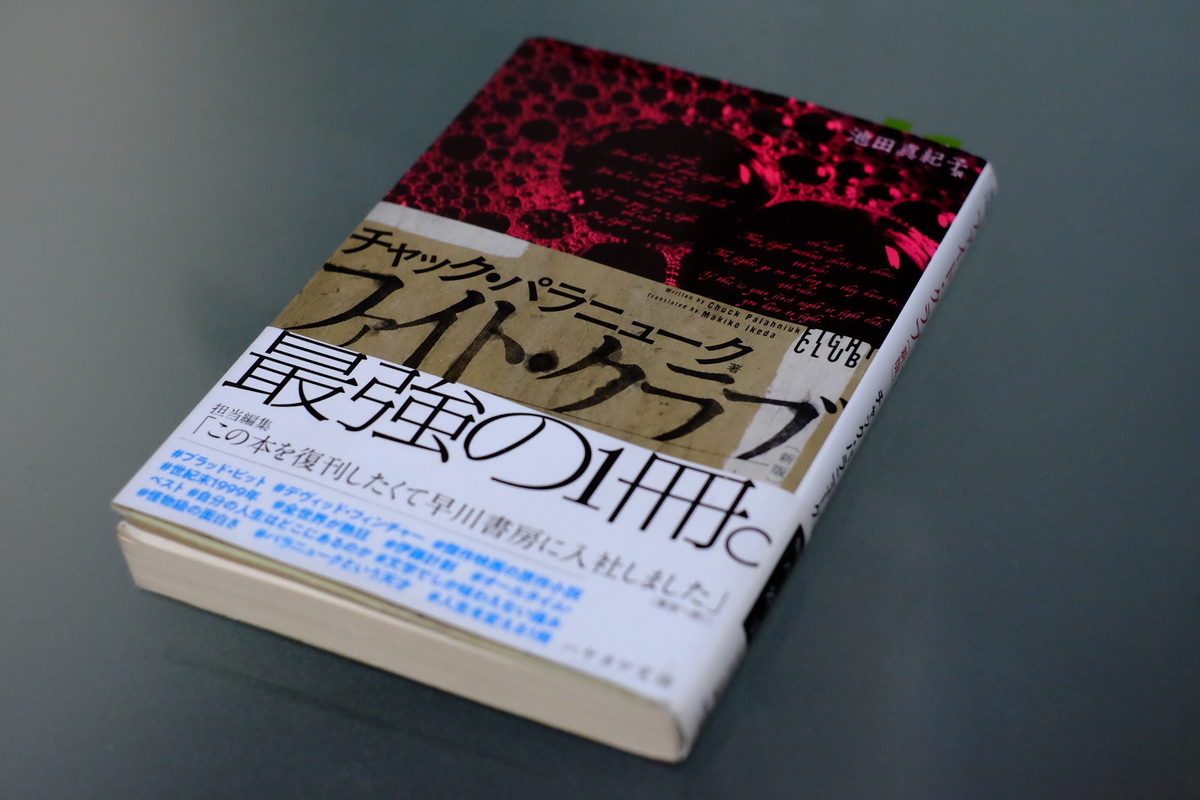私が故郷の宮崎県出身のヒーローとしているのが安井息軒、上杉鷹山、小村寿太郎、高木兼寛の4人なのですが、吉村昭先生がそのうち二人、小村寿太郎『ポーツマスの旗』、高木兼寛『白い航路』を上梓されているのがなんとも誇らしい気持ちです。
高木兼寛を題材とした『白い航路』を読みました。といっても読んだのは数ヶ月前ですが。
高木兼寛という人物は大久保利通、西郷隆盛、大隈重信、伊藤博文、森鴎外、小村寿太郎、東郷平八郎と同時代を活きた明治の海軍医です。ペリー来航の直前、1849(嘉永2)年に宮崎市高岡町穆佐で薩摩藩郷士・高木喜助の長男として生まれました。優秀だった兼寛は貧乏でしたが地元の塾に通い、地域の応援で薩摩藩の医学校に進学して戦医として戊辰戦争に従軍します(ここらの経緯は海軍少将の高木惣吉・・・熊本出身のジャックナイフで太平洋戦争の終結に向けてインテリジェンス活動をしていた、私にとって二人の「高木」を並べると本当に興味深い)。戦地にて当時でいうと最先端のバキバキの西洋医学を駆使して戦争負傷者の治療にあたる英国領事館の医師ウィリアム・ウィリスの技術に感銘を受けて西洋医学の道を目指すことになります。
西洋医学といっても兼寛はとりわけイギリスの医学を学ぶことになります。留学先もイギリスでした。当時の医学界は研究至上のドイツ医学派、実践のイギリス学派に分かれていたようです。ドイツ学派の医師と言えばコッホ研究所で学び陸軍医総監まで勤めた森鴎外(森林太郎)です。
学派もことなるこの二人は当時の日本の軍人が何十万人の単位で命を落とす「脚気」の原因について対立することになります。結果について簡単にまとめます。
人物 高木兼寛 森鴎外
所属 海軍 陸軍
脚気の原因についての主張 栄養不足 伝染病
日清戦争の脚気死亡軍人数 0 4,064
日露戦争の脚気死亡軍人数 3 27,800
死亡者数統計の出典:https://www.stat.go.jp/library/pdf/column0006.pdf
なんとも顕著な違いです。これは学術的根拠がまだ弱かったとはいえエビデンスベースで実験を繰り返しタンパク質不足(実際はビタミンB不足)が脚気の原因があると仮説立て軍人の食事の改善に勤めた海軍すなわち高木兼寛と、ドイツで学び伝染病説をとった森鴎外と「白米至上主義」に固執した陸軍との差から来たものです。
白米至上主義・・・少々ピンとこない言葉かもしれませんが、明治でも白米は非常に有難がられていた食品で、軍人は食費を支給されても目一杯米を購入してその他の副菜、肉、魚などには目もくれずお腹いっぱいにご飯を食べていました。都市部の生活水準の高い人々は米飯食中心で脚気患者が多く、地方の粗食な人々のほうが罹患率は低かったのです。推測ですが江戸から明治に続く支配構造の強化のために稲作中心の国土像=瑞穂国日本というイメージが連綿とプロバガンダされていたせいで、ヒエラルキーの上から下まで自家中毒を起こしていたのでしょう。中世日本の実態はそれとは異なる(生産品目はもっと多様で、年貢も様々な農作物や海産物、狩猟品、工芸品で納められていた)ということは網野善彦著『「日本」とは何か』(講談社)に詳しいです。
私がこの吉村昭の小説で最も興味深く読んだ部分がこの陸軍の白米至上主義への固執です。まるで天下り先の保健所と感染研を守るためにPCR検査抑制を掲げて、新型コロナ感染症対策のグローバルスタンダードを無視し続けそのパラダイムを頑なに変えない厚生労働省と分科会のルポタージュを読んでいるような生々しさなのです。
兼寛は上記の通り海軍の脚気死亡者減に多大な功績を残し、海外のアカデミーからも相当な評価を得ました。ところが、日本国内の学会からは激しい批判に晒されます。海軍の兵食改善は独自のもので、日本の医学会でオーソライズされたものにはなりませんでした。そして兼寛の学説を批判していたのが森鴎外です。
結局、日本の脚気研究がその原因をビタミンB欠乏と認めたのは森鴎外が死去した大正11年から4年後の大正14年です。森鴎外は死ぬまで「誤った学説」を固持したままだったのです。とはいえ、森鴎外ともあろう人物が当時の海外の論文や海外アカデミーの兼寛への評価がその耳目に入らないわけはなかったはずです。彼ももしかしたら「自分・・・間違ってるかも・・・」と思っていたのかもしれません。本作には森鴎外が上司にシバかられる非常に面白い場面があります。
七月四日、脚気病調査会の発会式が陸軍大臣官邸でもよおされた。
陸軍大臣寺内正毅は、立って挨拶をした。初めに、調査会が陸軍大臣の監督下におかれたのは、陸軍に脚気患者が多く、そのための研究も積みかさねてきたので研究対象にめぐまれている関係で陸軍の管轄としたと述べ、諒承をもとめた。
寺内は、陸軍が調査会の研究に全面的に協力すると約束した後、
「尚、一言すべきことがある」
と言って、かれがこの調査会を設立した動機について率直な発言をした。
「私は、二十年来の脚気患者である。二十年前には脚気専門の漢方医遠田澄庵氏の診療をうけたこともあるが、その後は、今日まで麦飯をとりつづけてきている」
寺内の演説に、森会長(=森鴎外)をはじめ委員にえらばれた陸軍衛生部員たちは表情をこわばらせた。
寺内は、言葉をつづけた。
「私は、麦飯を効果があると信じているので、日清戦争の折、運輸通信部長の任にあったので、わが軍隊に麦食を支給した。ところが、軍医総監であった石黒(忠悳)男爵から、何故に麦を支給するか、麦飯が果して脚気に効果あるか、などときびしく詰問され、遂に麦の供給を中止したことがある」
そこで言葉を切った寺内は、森(=森鴎外)に視線を走らせた後、
「当時、この席におらるる森医務局長なども石黒説賛成者で、私を詰問した一人である」
と、言った。
森は身じろぎもしなかったが、その顔からは血の色がひいていた。(下巻 P279)
いやぁ面白いですね。森鴎外の非常に人間らしい側面が描かれています。綿密な取材を踏まえて執筆をしますし、わからないことはわからない!と『熊嵐』では荒涼とした三毛別の闇のようにぼっかりと描写の空白を作っていた吉村昭が、なんの資料も無くこういった肉付けをするとは考えられませんので、きっとこの場面の記録があって、森鴎外は本当にこんな風だったのだろうなと想像しています。
嵐山光三郎『文人暴食』の坪内逍遥の章で嵐山は森鴎外のことをこう書いています。
ドイツ帰りのケンカ屋鴎外はあたりかまわずつっかかる乱暴医師であった
要するに、才能もステータスもありながら少々「イキり」の過ぎた人物だったのでしょう。作品『舞姫』でも往訪で調子こいて舞い上がっているテンションと卑屈さのコントラストが描かれています。
そんな森鴎外が、1914年(大正3年)に『安井夫人』を上梓しています。瞑目する8年前。題材となっている安井夫人とは高木兼寛と同じ宮崎県出身の近代漢学の祖である安井息軒のパートナーです。果たして文豪森鴎外が高木兼寛との確執、脚気病の原因に関する議論、膨大な陸軍軍人の脚気病死者数を抜きにして『安井夫人』などという題材を選び得たでしょうか。
私はなんとも深い業のようなものを感じてしまうのです。
【余録】
少々森鴎外の話が膨らみすぎたので高木兼寛の歴史上のすれ違いをかいつまんでご紹介します。やっぱりエリートの出会いは凄い。
薩摩藩の医学院で学ぶ兼寛が西洋医学の道に進むことができたのは明治3年(1870年)よりイギリス人医師ウィリアム・ウイリスに師事したからであるが、そのウイリスを招聘したのは大久保利通と西郷隆盛である。(上巻 p163~)そのウイルスは1861年より駐日英国公使館付医官として日本で働いており、着任の翌年1862年には生麦事件に遭遇する。知らせを受けて現場に急行し、犠牲者の一人チャールズ・レノックス・リチャードソンの死亡を確認した。リチャードソンに止めを刺した海江田信義は桜田門外の変で井伊直弼の首級をあげた有村次左衛門の実兄。(上巻 p72~)
明治8年(1875年)イギリスのセント・トーマス病院に留学。同イギリス派遣団にはイギリス海軍視察目的の東郷平八郎もいた。兼寛はセント・トーマス病院の看護師が優秀であることに感銘を受けるが当病院に付属する看護学校はその15年前の1860年にかのフローレンス・ナイチンゲールが創設したもの。(上巻 p265~)
当時、原因不明であった脚気で軍人が多く死亡しており、海軍医務局副長であった兼寛はその対策として食料改良を導入するよう明治16年(1883年)に明治天皇へ上奏する機会を得たが、その口利きをしたのが伊藤博文。(下巻 p99~)
海軍医の部下の仲介で資生堂創始者の福原有信と知遇を得て、明治20年(1887年)に帝国生命保険会社(現在の朝日生命)に出資し創設に参画する。(渋沢栄一の東洋生命保険は1936年に帝国生命保険に合併)(下巻 p187~)
明治22年(1889年)10月18日、霞ヶ関の海軍省へ人力車で移動中の兼寛が外務省の正門前に差しかかった時に、外務大臣大隈重信への爆弾による暗殺未遂現場に偶然居合わせ、大隈の応急処置を施す。(下巻 p216~)
明治24年(1891年)、警察官である津田三蔵がロシア皇太子ニコライを切りつける暗殺未遂=大津事件(湖南事件)を犯したことをうけ、事件の翌日に皇太子の泊まっている京都の宿へ派遣され治療を申し出た。(下巻 p225~)